1582年
(天正10)
|
小林八郎左衛門重定、滝川一益の甲州武田攻めに従軍。帰還後、朝明郡縄生村に200石の知行地を得る。
6月、本能寺の変(明智光秀の謀反により、織田信長本能寺で自害)
この頃、小林重定の養子重忠(千草忠治の第二子忠正)、織田信孝に仕える。 |
1583年
(天正11) |
織田信勝・羽柴秀吉ら織田家宿老と、織田信孝・柴田勝家・滝川一益の戦いで、北伊勢が戦場となる。
|
1614~15年
(慶長19~20) |
大坂の役(大坂冬の陣・大坂夏の陣)
小林八郎左衛門重定の養子平右衛門重忠、亀山城主松平下総守忠明に従い大坂へ出陣。 |
※ 大阪の役後
(年月不明) |
大坂の夏の陣後、重忠は家督を嫡子道順に譲り、道因と改名して菰野藩土方杢之助殿に仕える。(1654年承応3、83歳にて死去)
|
1618年
(元和4)
|
小林八郎左衛門重定、80歳にて死去。 |
寛永年中
(1624~44) |
徳川幕府が1615年(慶長20)に発令した大名統制策「一国一城令」に従い、小林道順、佐倉城を取り壊す。 |
1689年
(元禄2)
|
小林次左衛門(道因倅)と小林与市右衛門(次左衛門倅)は、津藩川原田組無足人として名が記される。(出典・「元禄二年川原田組無足人由緒改帳」『四日市市史第八巻』)
- 津藩領の「無足人(むそくにん)は、(他藩の郷士や地士などと同じで)在村していて知行や俸禄を得ない農兵を組織していた。地侍の系譜をひき、一年の大部分は農業に従事する上層農民であったが、苗字帯刀を認められ、他の者たちと区別された扱いを受けた。
 江戸期に入り、小林家当主は(佐倉村は津藩に属したので)藤堂和泉守在城の正月五日に、決まって五ツ時(午前8時)に挨拶に赴き、藤堂家家老が単独でその賀詞を受納する習わしであった。(出典・『西勝精舎聞書抄』山田教雄著) 江戸期に入り、小林家当主は(佐倉村は津藩に属したので)藤堂和泉守在城の正月五日に、決まって五ツ時(午前8時)に挨拶に赴き、藤堂家家老が単独でその賀詞を受納する習わしであった。(出典・『西勝精舎聞書抄』山田教雄著)
- 無足人(むそくにん) (出典・「日本民族大辞典」吉川弘文館)
藤堂藩の家臣団に組み込まれた在存の郷士の呼称。この無足人は平時は村に居住して農業経営を営み年貢を納入したが、有事には藩に軍役を務めることで百姓並み夫役は免除されていた。
戦国時代に知行を受けた侍の系譜を持つ者が取り立てられたが、近世中後期になると、庄屋や大庄屋を勤めた者や、献金によって取り立てられる者が増加した。1826年(文政9)に新規の無足人取立を停止し、無足人も百姓並みの夫役を務めることになった。
(関連ページ・『戊辰の役と当地区藤堂藩無足人の戦の跡』へリンク)
|
※ 1698年
(元禄11)
|
菰野藩に仕えた小林平右衛門重忠の子道因重信は、この頃御医師として金拾五両拾人扶持であった。(「菰野町図書館・資料室蔵)
|
| 幕末~明治 |
幕末から明治にかけて、次左衛門、勝之進、太郎と相続する。 |
1907年
(明治40年)
|
小林太郎氏は、菰野小学校教諭を経て、明治40年12月桜村の村長に就任。 |
1909年
(明治42)
|
10月、桜村村長の小林太郎氏は、神社合祀の心労により急死。 |
1914年
(大正3)
|
小林太郎氏夫人みさは駅前へ移住して煙草小売店を営む。
以降、佐倉城跡は細分化され宅地となっています。 |
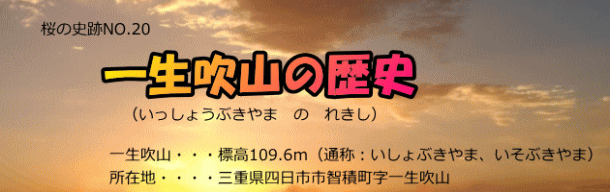
 (五七桐・小林城主家の家紋) 目 次
(五七桐・小林城主家の家紋) 目 次
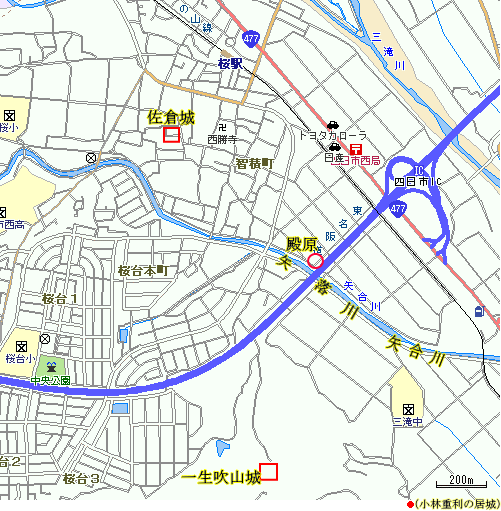
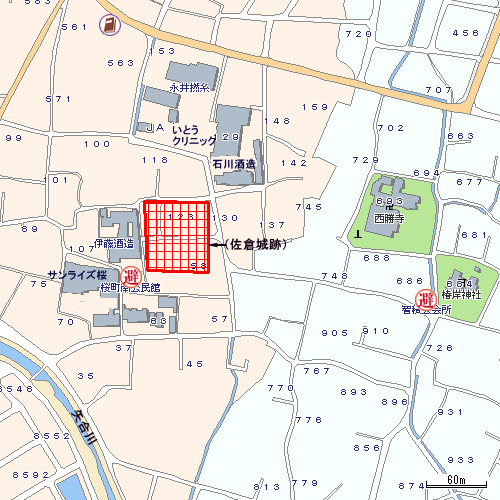
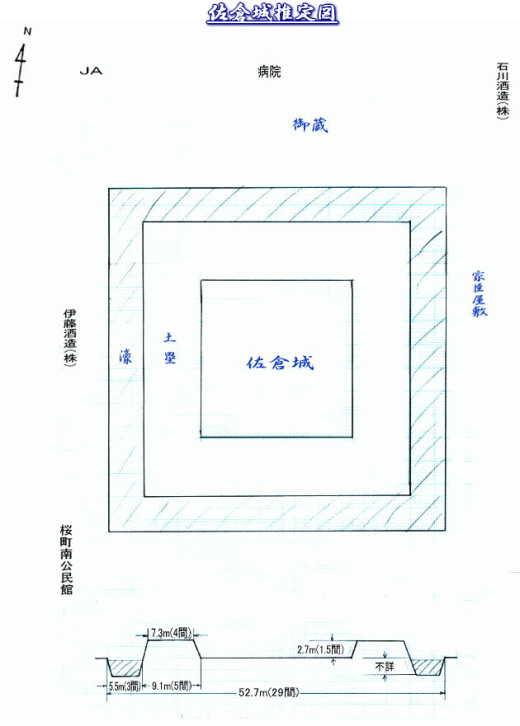




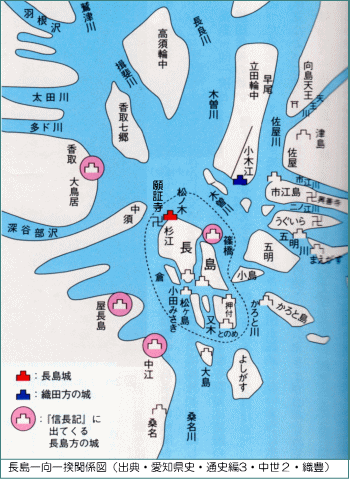 同年10月、長島門徒は織田信長の実弟・信興が守る一向宗抑えの「小木江(こきえ)城(現・愛知県愛西市)」を攻め、信興を自害に追い込んだ。
同年10月、長島門徒は織田信長の実弟・信興が守る一向宗抑えの「小木江(こきえ)城(現・愛知県愛西市)」を攻め、信興を自害に追い込んだ。